天才を育てる楽しみ
和戸川 純
少しでも時間があると、その時点でやっていることとは無関係なことを、ふと想ってしまう。それが私の楽しみ(のうちの一つ)になっている。
ただし、誰かと話をしているときにこんなことをやると、失敗をする。相手の言っていることが聞こえなくなってしまうのだ。私の目が、どこか遠くを見つめているのに気づいた相手は、一瞬けげんな顔をする。
けれども、目の前の相手がコンピューターならば、何も心配することはない。
というわけで、オーストラリアから日本へ帰国してからのことだが、コンピューターでとても現実的な作業(投資に関係したアナリシス)をやりながら、突然に昔のことを想いはじめてしまった。現実的な作業を続けるのが困難になり、作業を中断して、その思い出に集中することにした。
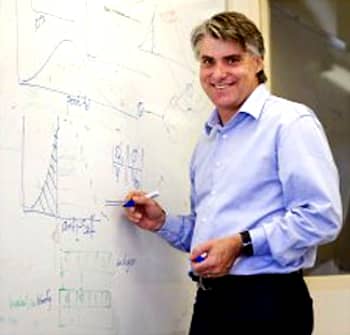
過去へさかのぼる旅は、オーストラリアへ行き着いた。 オーストラリアにおける二番目の職場は、W大学のScience Faculty(理学部ではない。理学部よりも専攻領域が広い。科学部とでも訳せばピッタリ)だった。主任研究員として仕事をした。バリバリの若手研究者といえた。
そこで、学生のフィルに出会った。
「あのフィルは、今何をしているのだろうか?ありとあらゆる情報が詰め込まれている、インターネット。調べれば、フィルが今どこで何をやっているのか、分かるかもしれない」
フィルのフル・ネームを使って、検索エンジンで検索をしてみた。あらためて感動。インターネットはすごい!すぐにフィルが見つかった。
運がよかった。フィルは、自分のページに顔写真を載せていたのだ。写真がなければ、同姓同名の他人の可能性が高い、と思わなければならなかった。何しろ、フル・ネームのフィリップ・ホジキンは、英語圏ではとても一般的な名前なのだ。フィリップ・ホジキンは掃いて捨てるほどにいる。
さらに運がよかったこと。50才に近いフィルの顔が、学生の頃とほとんど変わっていなかったのだ。太ってはいたが、写真を見た途端に、間違いなく『あのフィル』を見つけたことを知った
フィルは、メルボルンにある、Walter and Eliza Hall Instituteという基礎医学の研究所で、免疫の研究をしていた。大金持ちの夫婦の寄付によって作られた、免疫学研究では世界でトップ・クラスの研究所だ。
「クローン選択説」という理論で、免疫学分野で世界で初めてノーベル賞を受賞した、バーネットがこの研究所で仕事をしていた。免疫系で中心的な役割を担っているT細胞が、ここで発見された。抗体を産生するB細胞に関する発見や、コロニー刺激因子、それに臓器移植で問題になるMHCなどの発見もあった。
押しも押されもしない業績を上げ続けた、ノーベル賞受賞者を何人も輩出した研究所だ。
フィルは、この研究所の中心になる、免疫学部門の部門長をやっていた。メルボルン大学の教授も兼任していた。オーストラリア免疫学会の学会長でもあった。
この研究所のフィルのメール・アドレスへメールを送ると、すぐに返事がきた。
フィルが学生だったときに、私が研究の指導をした。学生だったフィルに、私が与えた研究テーマの延長線上で、フィルはずっと研究を続けていたのだ。 そのテーマに対する最終的な答が、もうすぐ出る予定だという、自信ありげなメールの内容。 私にそんなメールを書くことが、フィルにはとてもうれしかったはずだ。
私が、免疫学を一生の仕事にするきっかけをフィルに作った。一生涯の研究テーマを与えた私のことを、フィルはとてもよく覚えていた。フィルが卒業するときに、私がフィルに贈った一こま漫画を今でも持っている、ということまでメールに書かれていた。
私は研究者としてのフィルに、大きな影響を与えることができた。それ以上に、これから書くように、一人の人間としてのフィルの人生に、決定的な影響を与えたのだ。
フィルも、私にとても大きな影響を与えた。私はフィルのことを、昨日会った人のようにはっきりと覚えている。それは彼が、天才的な能力の持ち主だったからだ。一生に一人でも会えれば運がいい、といえる天才。
私が今までに出会った、天才といえる人は二人。フィルと上述のバーネットだ。
バーネットの「クローン選択説」をもとに、現代免疫学が発展した。バーネットは、免疫学のアインシュタインのような人だ。
私が渡豪して最初に勤めたのはメルボルン大学。そこで、駆け出しの研究者として仕事をした。同じ建物の中に、名誉教授だったバーネットがオフィスを持っていた。
その当時のバーネットには、研究や教育の義務はなかった。余生を送っている、全てを悟りきった、とても穏やかな熟年の紳士としか見えなかった。学生時代のフィルのような、抜き身の刀を思わせる危険な天才の雰囲気を、漂わせてはいなかった。
全くえらぶらず、若い日本人の研究者である私と、いつでも雑談をしてくれた。
他のスタッフは、高名なバーネットを煙たがって、明らかに距離を置いていた。バーネットが身近にいてうれしい私は、気遣いをしなかった。そんな向こう見ずな私を、バーネットは喜んでくれているように見えた。けれども、私の英会話も駆け出しだったので、会話中にいらいらしたことがあったと思う。
「なるほど、本物の天才とはこんな人なのだな」、と妙に感動したことを覚えている。

バーネットは高齢になってから奥さんを亡くした。その後、長い間バーネットの秘書をやっていた女性と再婚した。再婚して間もない時期に、私が実行委員長になって、メルボルン大学で「Japanese Night」という催し物を行った。バーネット夫妻を招待したところ、とても喜んでくれた(エッセイ37「海外では自由奔放な日本人」)。お礼にとくれたのが、東京大学出版会が出版した上の写真の本だった。バーネットの署名が入っている。
フィルとは違って、バーネットと私の間には広くて深い溝があった。私などよりも、ずっと高いところにいるバーネット。
オーストラリアの大学には教養課程がなく、1年目から専門コースへ入る。Science Facultyの4年目はHonors Courseと呼ばれ、日本の修士課程と同じことをする。このコースの学生は各研究室に配属され、与えられた研究テーマのもとに実験をして、卒業論文を書かなければならない。
フィルは私が指導することになった。これはフィルの希望があったためだ。
オーストラリア人の学生が、自分からわざわざ名指しをして、日本人を指導教員に選ぶのは珍しい。
日本語学科ならば、日本人教員を名指しにするのは、不思議でも何でもない。けれども、私が仕事をしていたのは、日本とは何の関係もないScience Facultyだった。
フィルが、有力教員ではない外国人の私を選んだ理由の一つに、権威者に対する反発の気持があった。 彼は反逆者だった。
人生経験がなく立場の弱い学生に、権威を示すのを楽しむ教員が、どこの国の大学にもいる。こういう教員は、学生を自分の指示通りに動かすことに、喜びを感じる。試験の解答、セミナーでの議論、レポートの内容などの全てを、自分が教えた通りにやることしか、学生には認めない。
普通の学生をこういう状況に置いても、特に問題は発生しない。なぜならば、与えられた教育内容をマスターし、試験で良い点数を取ることが大学でやること、と割り切っているからだ。
ところが、フィルのような学生には、こんな教え方は通用しない。ありきたりの知識と教え方に、全く興味を持っていないのだ。天才的な頭脳には、全てが分かりきっていておもしろくない。
そこで、フィルは当時こんなふうにやっていた。
試験では、低い点数だが、落第しないだけのぎりぎりの点数を取る。レポートも、わざと、クラスで最低の評価を受けるように書く。でも、落第点はつかないようにする。
こんなことができるというその事実だけを取っても、フィルに感心しなければならなかった。成績はクラスでビリだが、落第しないだけの点数をちゃんと取っている。こんな調整を思うようにできるということ自体が、フィルにとんでもない能力のあることを、示していた。
そうはいっても、
教授や准教授の評価では、フィルは箸にも棒にもかからない、全くダメな学生。何かというと反論をし、反抗的な態度を取り、しかも成績が最低なフィル。
それで、フィルが私を指導教員に選んだとき、フィルをダメ学生と評価していた教授、准教授は、きっと喜んだと思う。やっかい者の面倒を、見なくて済んだのだ。やっかい者は日本人に押しつけておけばいい。
私の研究室に、おしゃべりなオーストラリア人の女子大学院生がいた。彼女は、あちらこちらでいろいろな情報を収集してきては、私に教えてくれた。フィルはダメ学生という情報も、ちゃんと集めてきた。
「ジュン、本当にあんな学生を引き受けるの?とってもひどい学生だって、先生が言ってるわよ」
研究室に入り口から入ると、右側に、4畳半ほどの広さの三方がガラス張りの小部屋がある。これが実験室を眺めわたせるオフィスだ。
このオフィスにフィルを呼び、指導する側とされる側の、意志の最終確認をすることになった。この面接で、両者が納得をすることが配属のための条件になる。
フィルと初めて話をしたとき、私はとても驚ろいた。フィルの感受性が、ずば抜けて高いことがすぐに分かったのだ。私の言い分を、完璧に理解しただけではなかった。自分が考えていることを、私が間違いなく理解できるように、とても的確に説明した。
私が一つを話せば十を理解する。しかもこの十の中には、私が考えてもいなかったような意見が含まれる。
「これはタダの学生ではない」、と私にはピンときた。そして、タダの教員がこんな学生を前にすると、教員の立場から、自分の言い分を高圧的に押しつけてしまう状況を、はっきりと想像できた。 その結果、本人をだめにしてしまう。そんなこともすぐに理解できた。
こういう学生に、誰もが知っているようなことをやらせようとしても、全く興味を持つことがない。
次の日に、フィルに研究テーマを与えることにした。
テーマを考えるとき、私はフィルを学生とは考えなかった。
世界中の最先端の専門家が興味を持っている、大部分が未知の分野の研究テーマを与えることにした。
それは、私自身がとても興味を持っていたテーマだった。しかし、私がオーストラリア政府の医学研究基金から得ていた研究費で、カバーできる範囲の仕事ではなかった。免疫反応の中心に存在する液性因子が、免疫ネットワークにどのような作用を及ぼしているのかを、明らかにしようとする研究テーマだった。
この分野は、現在ではかなり明らかになっている。けれども、当時はほとんど闇の中。こんな研究テーマを、学部の最終学年の学生に与えたのだ。指導教員である、私にも指導できないような研究テーマ。
それを知った他の教員、特に免疫学が専門の准教授が、私を厳しく批判した。
経験のあるトップ・レベルの研究者でさえも、とても苦労しながら取り組んでいるテーマ。それを、よりによって学生、しかもダメ学生のフィルにやらせるというのだ。その准教授が、驚いたりあきれたりするのは、当然といえば当然だった。
「馬鹿日本人が、馬鹿学生に馬鹿げたテーマを与えたって、xxが言ってたわよ」、と上記の女子学生が私に教えてくれた。
他の教員が学生に与えたテーマは、授業としてやった実験室での実験を、延長したようなものだった。必ず答が出るという研究テーマ。それも、指導教員が知っている範囲の答が。
研究テーマを示したときに、私はフィルに結論を出すことを求めなかった。
「やれるところまでやればいいよ」
いかに天才的なひらめきを見せるフィルでも、わずか1年間で何らかの結論を出すことは、不可能なのは明らかだった。
私の信念はこうだった。大学では、その学生に合わせて、能力を最大限に引き出せるような教育指導を、しなければならない。その教育をもとにして、本人が、人生をかけたチャレンジをするための目標を、見つけることができれば幸いだ。
もっとも、他の平均的な学生を前にしては、私も他の教員のように行動した。答と答に到達する過程が、既に分かっているテーマを与えたのだ。私がフィルを別格扱いしたのは、私が考える最もチャレンジングなテーマを、フィルはこなすことができる、と判断したからだ。
フィルは、私が示した研究テーマにとても喜んだ。やっと、自分が全力投球でチャレンジできるテーマを、与えてもらったのだ。同時に、私が初めてフィルの能力を高く評価したことが、大学教員から、人間としての価値を認めてもらったような喜びを、フィルに与えたはずだ。
フィルは、私の意図を完全に理解した。免疫ネットワークの中心を攻める研究。世界中で激しい競争が行われている研究分野における、プロの研究者にとっても難しいテーマだ。フィルに対する私の要求は、最善を尽くすことのみ。
それからのフィルは、真夜中でも大学へ出てきて実験をした。 彼の研究を見守りながら、私は、フィルが天才的な能力の持ち主であることを、再び確認した。
最先端の研究論文を読むと、その論文の全体的な研究分野における位置づけを、すぐに理解するだけではなかった。その論文の中の一つの数字、一つの言葉の意味を、論文の著者自身よりも、恐らくより明確にとらえてしまった。
実験計画が、問題の解析のために適切なだけではなかった。出てきた結果の意味をたちどころに理解し、実験をさらにどちらの方向へ発展させればいいのかも、イメージとして示すことができた。
私は、フィルを私と同じプロの研究者として扱い、いろいろな議論をした。私が気づかないことも、鋭く指摘するフィル。そんな彼を、自分よりも経験と能力の劣った学生として扱うことなどは、とてもできなかった。私が知っていることは教えるけれども、逆の場合は教えてもらう。それしか選択の余地がなかった。
そんなこんなで、知的刺激がとてもたくさんあって、私の研究生活において最も楽しかった1年だった。
私から見れば当然のことながら、フィルの卒業論文は出色のできばえになった。全90ページの研究論文は、豊かな経験のあるプロの研究者の論文並み。全編にわたって論理がきちんと通っていた。
他の教員、特に一番厳しくフィルと私を批判していた免疫学の准教授は、フィルの高い能力の確証を眼前に突きつけられて、驚愕した。フィルの論文の価値を認めざるを得なかった。
それまで、試験やレポートの結果が、クラスで最低だったフィル。しかし、卒業論文では、Science Facultyで歴史上最高という評価を得たのだ。
その卒業論文を、私は今でも手元に持っている。今読んでも、実験の流れと論理はとても正確だ。すぐれた論文が古くなることはない。
天才フィルは、研究以外でも、若いうちからいろいろな人生経験を積んでしまった。性格が穏やかでかわいい同級生と、学生結婚をしたのだ。そして妊娠。
しかし、ネットで見つけた写真のフィルには、同年代の他の人よりも早く駆け抜けた人生の疲れはなく、まだ若い。私と一緒に研究をしていた、学生時代のフィルが、そこにいた。
日本へ帰国してから、私は独立行政法人の研究所で仕事をしていた。フィルをネットで見つけてから、仕事で同僚とともにメルボルンへ出かけた。勿論、フィルには事前に連絡をした。
フィルは、自分の車で空港まで出迎えてくれた。大分肥ったが、あの目が輝いている学生時代のフィルはそのままで、その目は私しか見なかった。
メルボルン市内の何箇所かの訪問先へも、一緒についてきてくれた。帰国時にも、自分の車で空港まで送ってくれた。その途中で、ワイン・ショップへ連れていってくれ、一番いいワインを選んでくれた。
研究所の同僚は、「とても驚いた」と帰りの飛行機の中で言った。免疫学会長、世界でトップ・クラスの研究所の部門長、大学教授のオーストラリア人が、ここまで時間を割いて私の面倒を個人的に見てくれた。素直に考えれば、確かに誰でも驚く。
しかし、私とフィルの関係に、社会的な地位が影響することはない。私がいなければ、大学生活で落伍し、人生の敗者になる可能性が高かったフィル。私がフィルの能力を認め、免疫学領域へ引き込んだおかげで、フィルは世界でもトップ・クラスの研究者になった。
現在という時間は、二人の人間の過去の偶然の出会いの延長線上に、あるに過ぎない。
私は、自分の影響によって、一人の人間の人生の価値を、ここまで高めることができたことに、自分のことよりも喜びを感じている。
フィルは、学生時代のあの論文を、研究所の自分のデスクの上の一番よく見える棚に、飾っている。その論文には、指導教員だった私の署名が入っている。訪問者である私たち二人にその論文を見せながら、「これが私の研究の出発点です」、とフィルが言った。
フィルの現在の研究は、理解するのが誰にも難しい。コンピューターをフルに使って解析することにより、液性因子と免疫細胞の反応の全体像を、描き出そうとしているのだ。即ち、免疫系の壮大な理論構築に取り組んでいる。
東京の某大学で仕事をしている友人が、フィルとの共同研究を望んで、私に接触してきた。私は友人をフィルに紹介した。
友人は、共同研究の内容を検討するために、フィルの研究論文を読んだが、フィルの仕事を理解することができなかった。共同研究はあきらめざるを得なかった。
ここで再び否応もなく、フィルの天才性が証明されることになった。フィルの研究を理解できる研究者は、世界でも多くはないと思われる。最高のコンピューター理論を駆使した、生物学研究の過程は複雑だが、結論は恐らく単純になる。フィルには、そうしなければならないことは、自明の理と思われる。
フィルの研究成果がノーベル賞に結びつくことを、私は願っている。
最後に、ひとこと付け加えておきたい。
天才を育てるひとは、天才である必要はない。天才とは何かが分かっていればいい。そして、どうすれば天才が伸びるのかも。それだけで十分だ。
活躍の場を適切に作ってやれば、あとは天才は自分で自分を伸ばす。